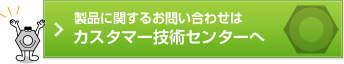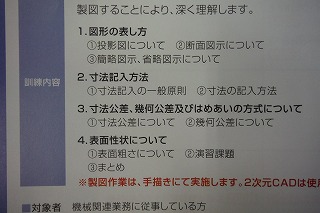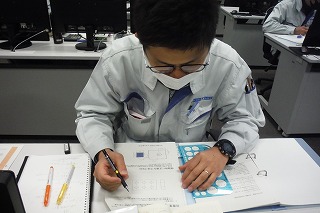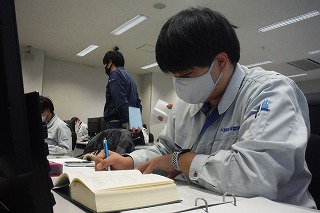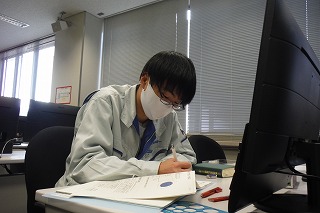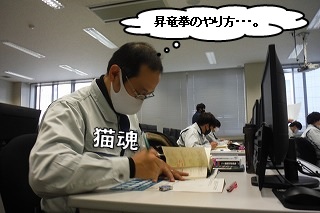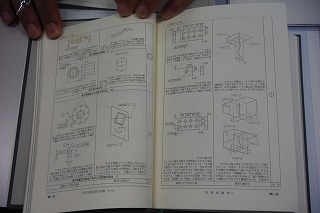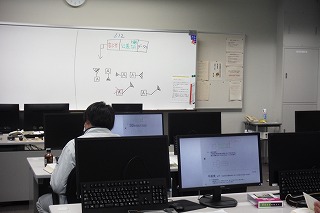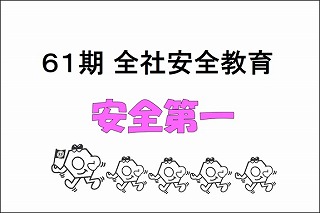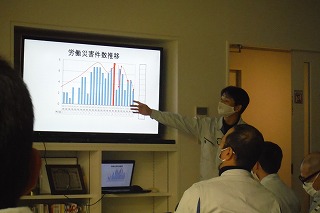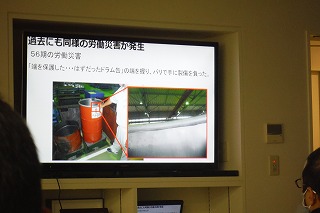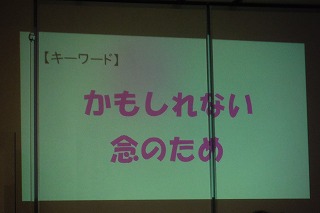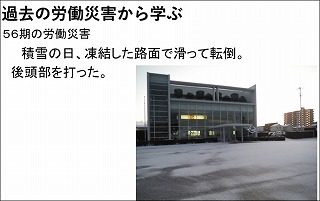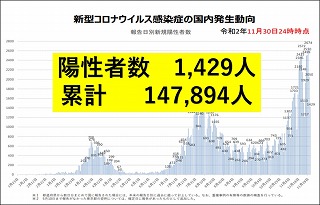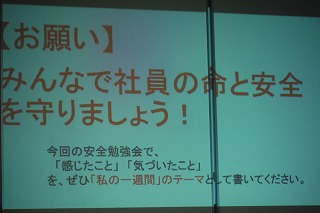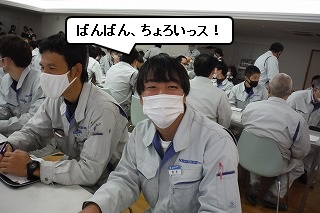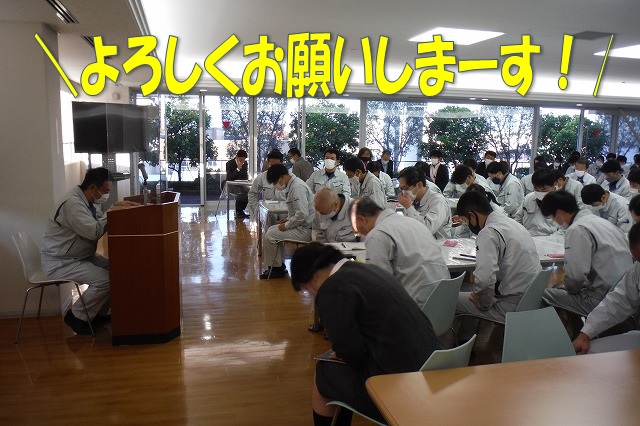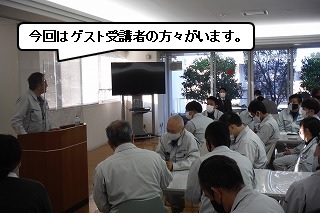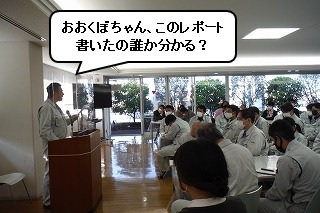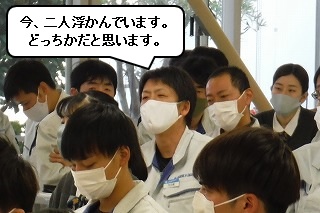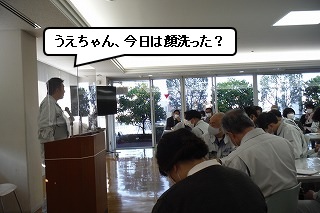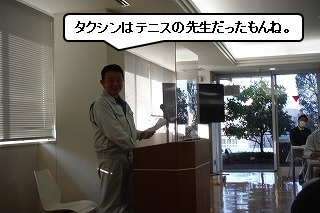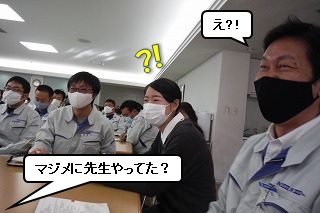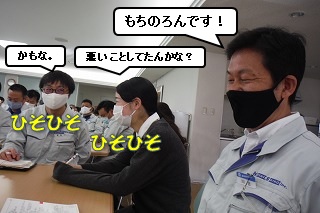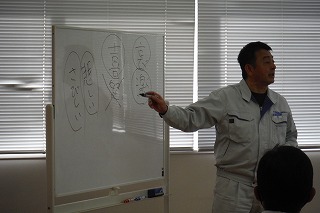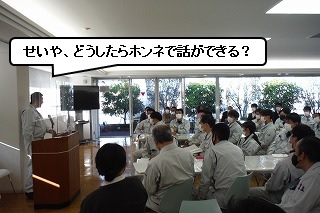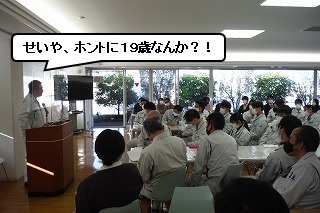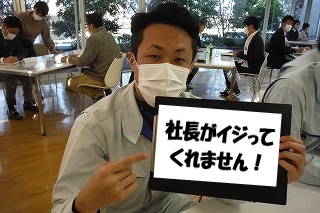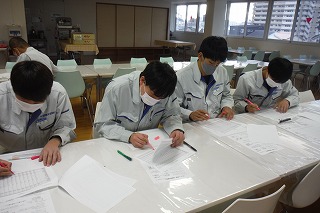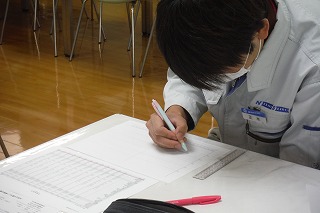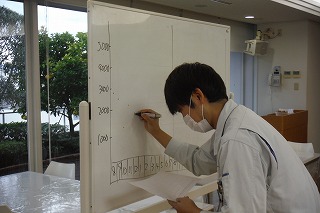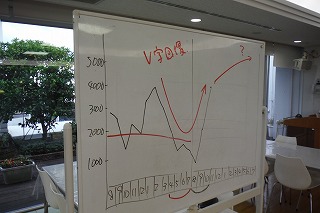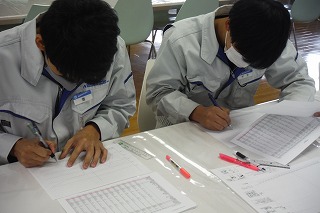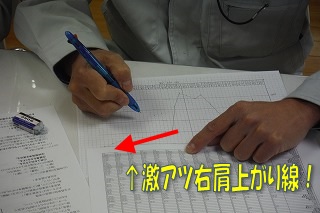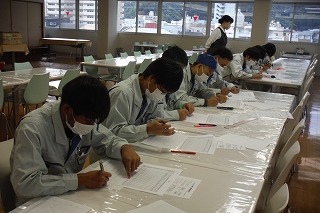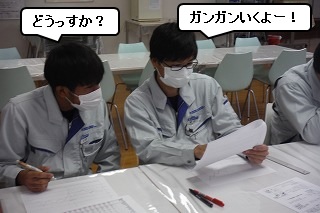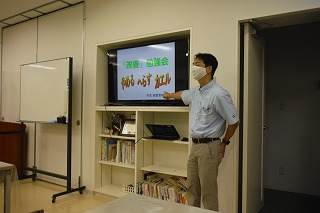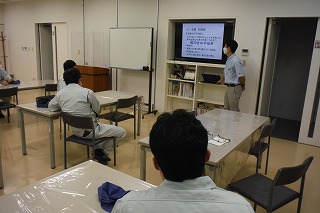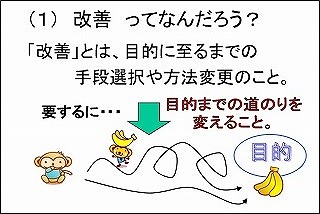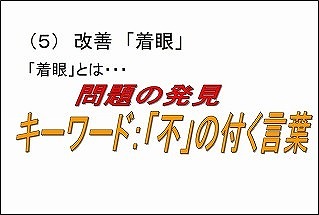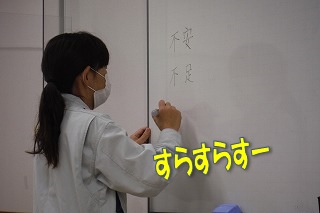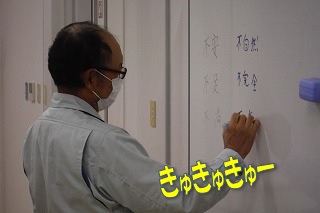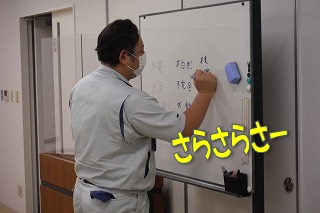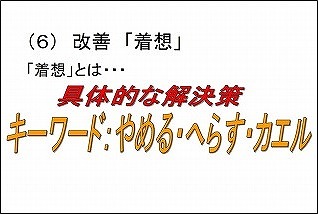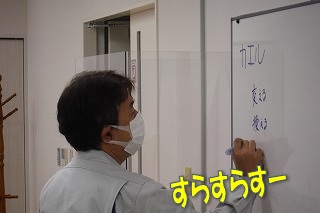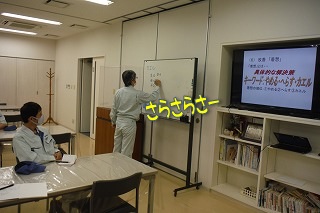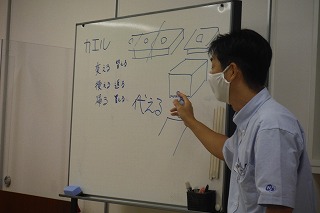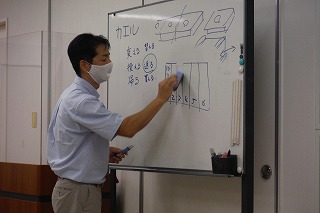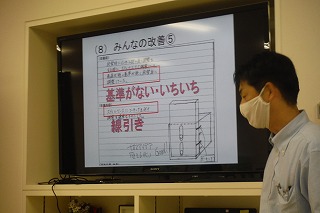教育 の記事一覧
2010/06/01 からあなたは累計  人目の訪問者です。
人目の訪問者です。
(本日は  番目のアクセスです。 また昨日は
番目のアクセスです。 また昨日は  人のご来場者がありました)
人のご来場者がありました)
2020.12.24
ポリテクセンターで製図を学ぶ
|

|
12月のある日、ポリテクセンター徳島で「製図を学ぶ」セミナーがあり、西精工社員たちが学んできました!
今回は西精工社員オンリーで学ばせてくださったんですよ。
ありがとうございます!
なので今回はナベさんが写真を撮りに行ってくれました!
|
|
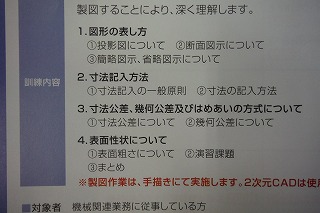
|
|
ってことでポリテクセンター!
研修室に潜入してくれました!みんなマジメに製図を学んでいます!
今回は「製図の基礎」ということで、CADとかじゃなく、手描きの製図です!
|
|

|

|
|
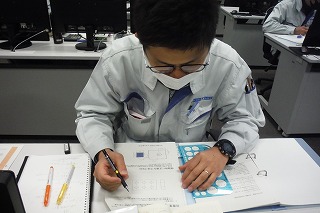
|
みんなの真剣な様子をどうぞ!
若手からおっさん(王子)まで、幅広い顔ぶれですね!
実際に製図に携わる人は少ないですが、製図を学ぶことで、図面そのものや、図面に込められた「意図」を読み取ることができるようになります。
これ大事! |
|
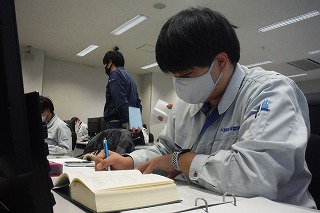
|

|
|
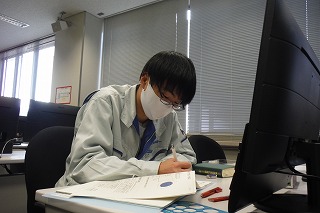
|
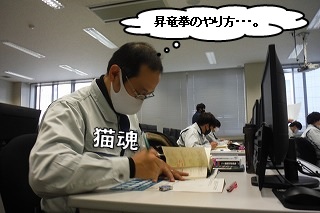
|
|
みんなの出来栄えが気になるはまださんがチェック!
うまく描けてますか?
|
|

|

|
|
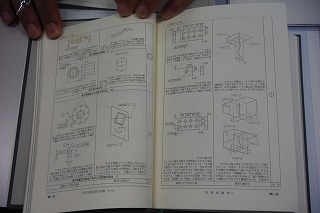
|
←のような立体図を平面図にするためには「空間認識」がすごく大切!
難しい課題でたくさん製図を学べたセミナーでした!
みんな、お疲れ様!
ポリテクセンターの皆さま、ありがとうございました! |
|
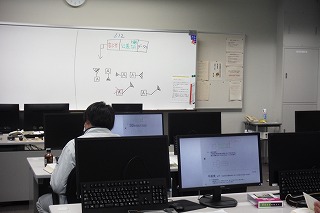
|

|
W 
2020.12.17
安全第一!安全勉強会
|
先日、土成工場で安全教育を実施しました!
仕事をする上で、何よりも最優先されるのが「安全」です!
この安全教育も「安全第一」の取り組みの一環なのです。
|
|
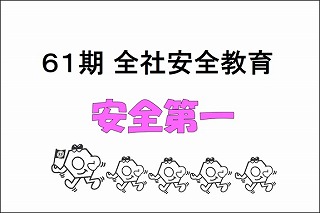
|
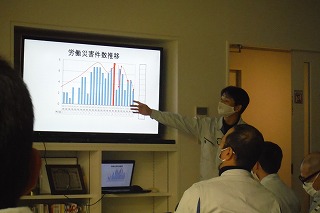
|
|

|

|
|
しかし年に数件は、手を切ってしまったり、ぶつけてしまったりというケガが発生しているんです。
それらケガの発生状況や、そこから学ぶもの、対策するものをみんなで共有します。
|
|

|

|
|
また、過去に起きた労働災害もまた「学びの教材」です。
同じケガをしないように、過去のケガ及び、その対策がきちんと守られているかもリマインドします。
下の写真は、数年前にドラム缶の端で手を切ってしまったケガ。
ちゃんと端をゴムホースで巻いて保護していたのですが、バリがはみ出てていて、そこで手を切ってしまいました。
ケガ防止をしている「つもり」でも、思わぬところに「まさか」が潜んでいるんです。
|
|

|
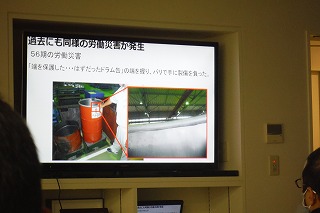
|
|
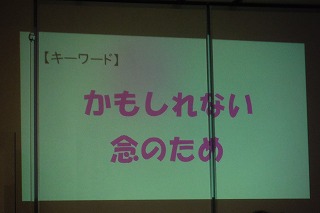
|
各職場では「KYT:危険予知トレーニング」を行っています。
そのKYTのキーワードになるのが、
「かもしれない」 「念のため」
です!
このキーワードはすごく大切!
ちなみに下の写真は冬ならではのケガ。
凍結した路面ですべって、頭を打ったケガです。 |
|

|
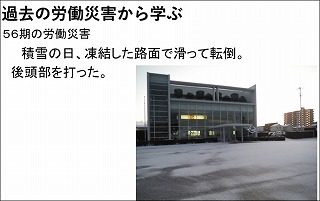
|
|
更には、新型コロナウイルス感染予防についても、会社のガイドラインをリマインド。
まさか、安全教育で感染予防のことを取り上げる時代になるなんて・・・。
新型コロナウイルスが終息する日が早く来ますように!
|
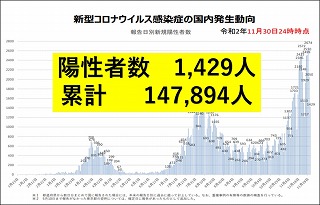
|
|

|
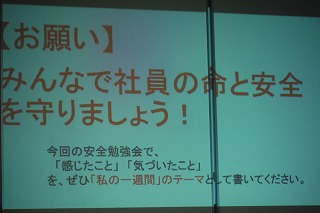
|
|
とにもかくにも、最優先は「安全」!
みんなの力で労働災害の無い「安全な職場づくり」をこれからも進めていきます!
安全第一!
|
W 
2020.12.16
リーダーシップ勉強会:ジェラシーばんばん!
|

|
この日は本社でリーダーシップ勉強会。
11月は係別面接があり、リーダーシップ勉強会はお休み月だったので、2カ月ぶりの勉強会です!
勉強会開始前のオフショット。
この日もばんばんは「Ride on ZOO」!
(Ride on ZOO=図に乗ってる)
だがしかし!
だいち後輩が更に「Ride on ZOO」らしいです。(ばんばん談) |
|

|
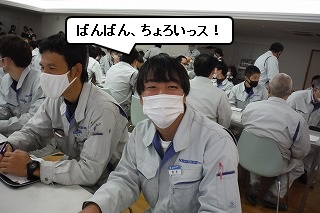
|
|

|
ばんばんやだいち後輩とは違い、もりもんは「学ぶ姿勢」に溢れています!
そんなもりもんの思いも乗せて、社長が講師をしてくださる、今月のリーダーシップ勉強会が始まります!
よろしくお願いします! |
|
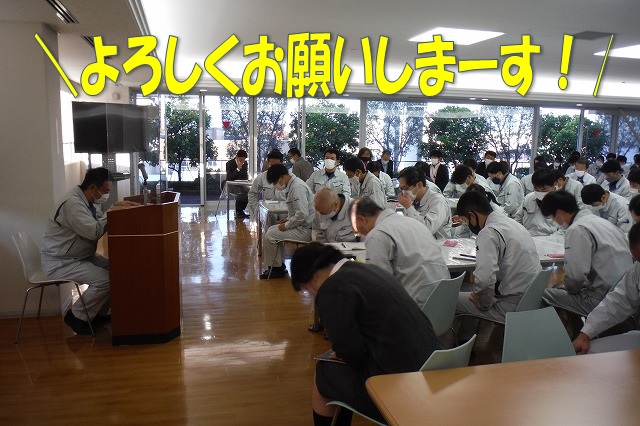
|
|
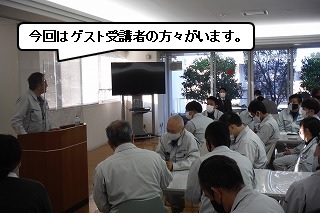
|
この日は社長が講師をされる「ミッションステートメント作成セミナー」がこのリーダーシップ勉強会の後で実施されました。
ってことで、ミッションステートメント作成セミナーを受講される方のうち、一部の方がリーダーシップ勉強会を一緒に受講されているのです。
わざわざ朝早くからお越しくださり、ありがとうございます! |
|

|

|
|

|

|
|
いつものように、リーダーシップ勉強会の内容を少しだけ(・・・と書きながら、いつも「少し」じゃない)紹介します!
まずは前回(10月)の勉強会のおさらいから。
「仕事に感情を持ち込む」・・・ということ。
・ビジネスシーンにおいて出すのは「理性」であり、「知性」である。
「感情」を出すのはダサい・・・とよく言われます。
でも「感情:喜怒哀楽」を押し殺して働くと、そこにはストレスが生じてきます。
そのストレスに耐えて!耐えて!耐え抜いて・・・一気にそのストレスが噴き出すのです。
激しく激昂したり(いわゆる「ブチギレ」)、逆に沈み込んだり。
そうではなく、適度に感情を出す。「上手に感情的になる」ということが大切。
そして自分の感情を共感してくれる仲間がいると、すごく安心を感じられます。
・でもこんな人いませんか?
相手が全然無表情・・・。何を考えているのか分からない。
「感情を出せよ!」と相手を変えようとしても、そうそう相手を変えることはできません。
そんな時には、「あなたが笑えばいい」のです。
感情は人から人へと伝染します。「ミラーニューロン」という現象だそうで、脳科学でも立証されているそうです。
周りにポジティブな人がいるだけで、その雰囲気は楽しくなります。
・上手に感情を出すための「3つ」
①周りをイヤな気分にさせる感情は抑える。
②不安や悲しみの感情は押し殺さなくていい。
③嬉しい時は思いっきり笑顔を見せる。
|
|

|

|
|

|
みんな知ってるグーグル(Google)。
そのグーグルで「生産性の高いチームの条件は何か?」の研究をした「プロジェクト・アリストテレス」というのがあります。
それによると、生産性を高める因子は「心理的安全性」なんだそうです。
心理的安全性とは、そこにいても「罰せられない」「否定されない」「バカにされない」「邪魔にされない」・・・ということ。 |
|
そして、自分の職場が心理的安全性を持っているか?が分かる「7つの質問」というのがあるそうです。
(ぜひ自分の職場で考えてみてくださいね)
①ミスをしても非難されない(特に人間性を否定されない)。
②難題やネガティブなことでも言い合える。
③「異質」であってもメンバーから拒絶されない。
④安心してリスクを取った行動ができる。
⑤チームメンバーに助けを求めることができる。
⑥仕事の成果を軽んじるメンバーがいない。
⑦自分の能力や才能が活かされている。
これらに当てはまっていると「心理的安全性がある職場」なんだそうです。
では、どうすればそんな職場になるのか?
それが「自分の感情をさらけ出す」です(でも「怒り」の感情はNG)。
強がらなくていい。共感してくれる仲間がいるのだから。
た・だ・し!
普段から「信頼関係」があるからできること!
信頼関係が無いと、自分をさらけ出すことは出来ないし、共感もされません。
|
|

|

|
|

|
たぶん書き過ぎています。
でも止まらない。(社長、ごめんなさい)
ここからは、社員が書いたレポートから学びます。
「感情を出すのが苦手だったけど、感情を出せるようになってきた」
といった内容でした。 |
|
社長がおおくぼちゃんに質問します。
「これ、誰のレポートか分かる?」
おおくぼちゃん、ほぼ誰が書いたのか把握している様子。
社長が紹介してくださるレポート、たいてい同じチームの人や関わりが深い人は「あ、あの人のレポートだ」と分かっちゃうんです。
|
|
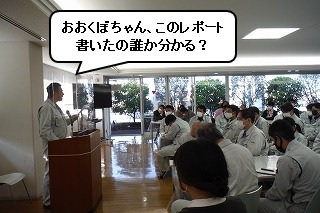
|
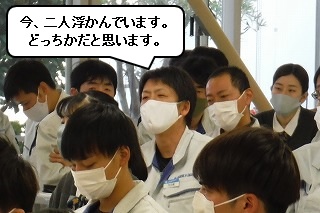
|
|
人は「これ」と「それ」を区別できません。
ちょっと抽象的ですね(汗)
例えば、きめ細やかな掃除をする人は、仕事っぷりもきめ細やか、ということ。
なので普段からの言動を磨いていかないといけません。
習慣化できないことも、まずは「意識的にやる」。
そしてくり返していくうちに「習慣化」する。するとそれがその人の行動となり、それをしないと「気持ち悪い」と感じるようになります。
例えばシートベルト。
最初は「シートベルトをしないと警察の人に止められる」から始まります。
でも習慣化してくると、無意識にシートベルトに手が動くし、シートベルトをしていないと気持ち悪くなりますよね。
「朝起きて、歯を磨いて、顔を洗う」というのも同じ。
小さい子供のうちは、親に叱られながら嫌々やるけど、気づけば習慣化して、毎朝やらないと気持ち悪いと感じますよね。
それです!
うえちゃんもちゃんと習慣化しているそうですよ!
|
|
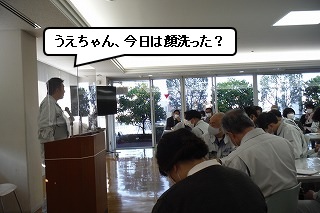
|

|
|
「多様性」の話になった時、タクシンがイジられます(笑)
タクシン、以前はテニスのインストラクターをやってました!
|
|
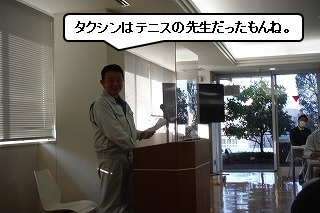
|

|
|
前職で素行が悪くなかったか?を掘り下げられ、困るタクシン。
それを怪しむゆーみん。
|
|
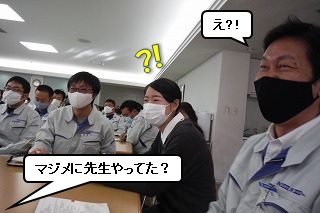
|
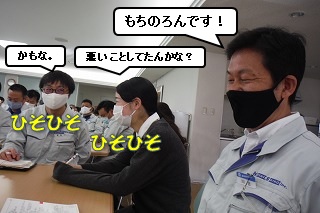
|
|

|
レポートの中に、子供に対して厳しく叱責してしまい、後悔したことが書かれていました。
ここで「感情を出す」ことについて説明してくださいます。
感情の主なものは「喜怒哀楽」です。
この4つの感情の中で、出してはいけないのが「怒り」の感情。
この「怒り」は変換できるのです。
「悲しい」とか「寂しい」が本当の感情なのです。 |
|

|

|
|
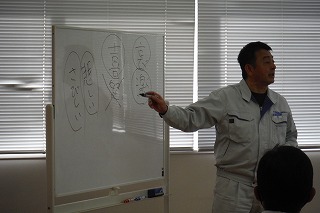
|
なかなか難しい「ホンネの対話」。
どうすればそれが出来るのか?
社長の投げ掛けにステキ回答をするせいや!
「その先に何があるか?」
その先に、チームの成長や相手の成長があるならば、ホンネで対話ができます。
|
|
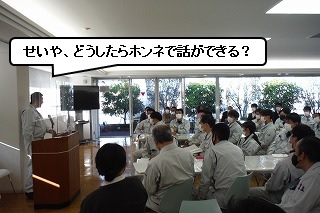
|

|
|
しかし、「自分が」「自分のために」というエゴのためにホンネをさらけ出すと、周りの人はうんざりしちゃいます。
せいや、19歳にしてちゃんと分かってるのがすごい!
せいやが19歳なことを疑う社長(笑)
|
|
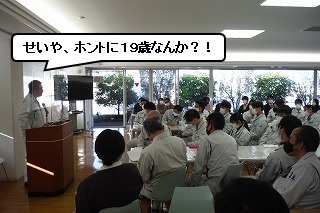
|

|
|
まだ今月のリーダーシップ勉強会を受講していない人がいるのに、めっちゃ内容を書いちゃいました(汗)
改めまして、社長、ごめんなさい・・・。
今回もリーダーシップ勉強会をしてくださり、ありがとうございました!
|
|

|
|
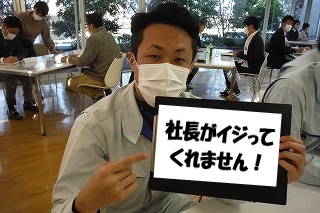
|
【おまけ】
今回、まったくばんばんはイジられず。
社長、イジられなくて寂しいそうです。 |
W 
2020.11.24
アメーバ経営勉強会:どうしたい?
|
先日、成型1係でアメーバ経営の勉強会を行いました!
この勉強会では、自分たちのチームがどのくらい稼ぐことが出来ているのか?それを数字とグラフを使って再認識していきます。
|
|

|
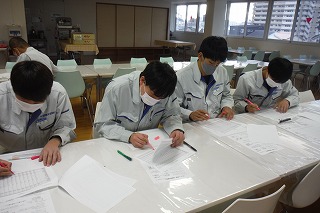
|
|
まずは前期一年間の実績をグラフ用紙にプロットして、折れ線グラフを描いていきます。
ここは「手描き」なのがポイント!
エクセルを使えばすぐにグラフは描けちゃいますが、「あえて」手描きすると、
・数字が良くなっているのか?
・逆に悪くなっているのか?
・なぜそうなっているのか?
・この時、何かあったっけ?
こういった気づきを得やすくなります。
アナログはアナログの良いところがあります。
|
|

|
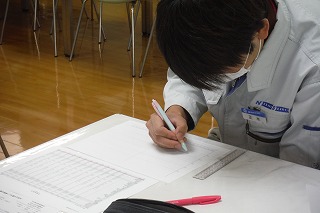
|
|

|
←同じチーム同士でグラフの形が合致しているか確認し合っています。
ではでは1班を代表して、けんちゃんがホワイトボードに折れ線グラフを描いてもらいました。
はい、4月くらいから「新型コロナ」の影響をモロに受けて、大きく収益を落としているのが分かります。
|
|
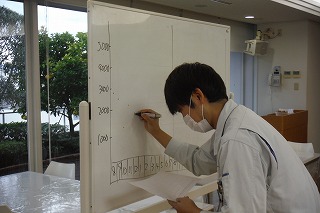
|
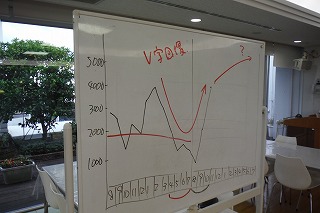
|
|
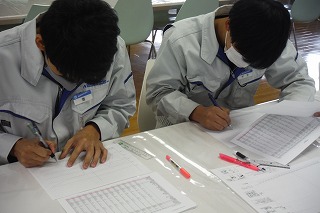
|
ありがたいことに、直近の9月~10月で仕事量は回復してきました。
さて、ここからみんなには
「この先、どうしたいの?」
を線にしてグラフに描いてもらいます。
みんな、どうしたい? |
|

|
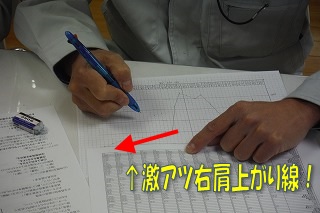
|
|
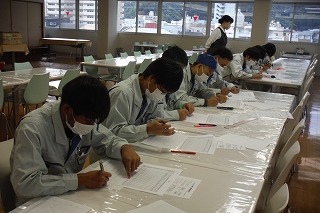
|
メンバーそれぞれに「こうしたい!」という思いがあり、それはたいてい「良くしたい」という思いです。
その思いを共有するのには、こういった数字やグラフにすると、すごく伝わりやすい!
自然とチームメイト同士が見せっこしているのが、成型1係のすごいところ! |
|

|
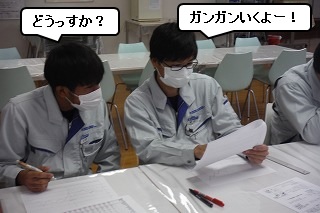
|
|

|
ここでいやらしく、実際に今期のマスタープランで決めた数字をプロットしていきます。
マスタープランを組んだ時は「新型コロナ不況」真っ只中だったこともあり、けっこう「こうしたい」と描いた線よりも下に線が引かれてしまいました。
この低いマスタープランを見直して、コロナ禍であってもお客様への価値提供を高めていこう!
そう誓い合った勉強会でした! |
|

|

|
W 
2020.10.19
改善勉強会:いちむらさんは「バリ伝」を集めていた
|
先日、旋削係で「改善勉強会」を実施しましたー!
「そもそも改善って何だろう?」
「改善はどういう考え方をすればいいだろう?」
これら「改善の基礎」を改めてみんなで学び、職場での改善活動を活性化させるのがネライなのです!
|
|

|
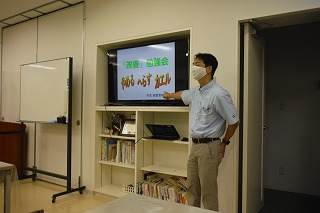
|
|
「改善」は「目的」に至るまでの「手段選択」や「方法変更」のこと。
「やり方はひとつじゃないよ」ってことです。
「目的」を果たすための方法は、創意工夫次第でたくさんあります!
|
|
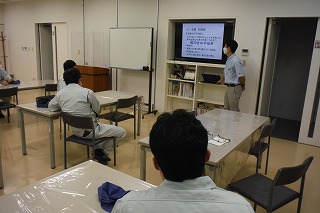
|
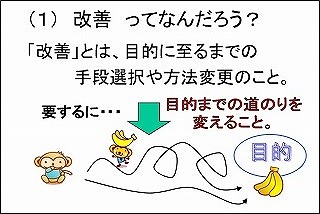
|
|
いざ「改善をする」となると、構えちゃう人も少なくありません。
そこで、改善を「3つのステップ」に切り分けて考えていきます。
その改善の3つのステップが、
「着眼」-「着想」-「着手」
です!
|
|

|

|
|
改善のステップ①では「着眼」・・・つまり、身近に潜んでいる「問題」をあぶり出します。
その「問題のあぶり出し」に活用するのが「不の付く言葉」なのです!
ってことで、いつものように、みんなに「不の付く言葉」を書き出してみてもらいました。
旋削メンバーみんな、スラスラ書いていきます!
すごくスムーズ!すごい!
|
|
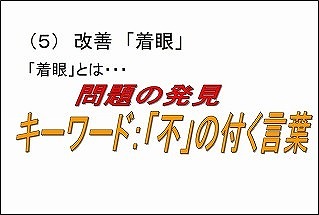
|
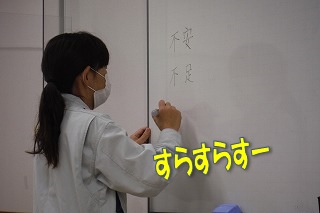
|
|
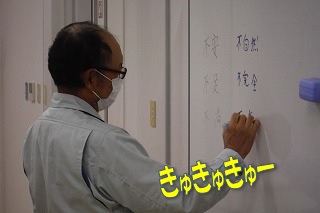
|
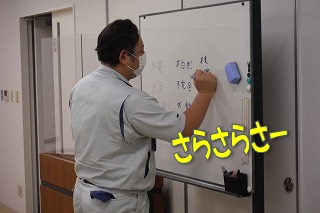
|
|
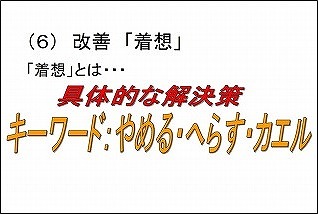
|
改善のステップ②は「着想」!
具体的な解決策を考えるのですが、そのヒントになるキーワードが、
「やめる・へらす・カエル」
です!
最上級の解決策は「やめちゃう」!
この「やめちゃう」解決策は、お金がかからない!スグできる!効果抜群!と言うことなし!
ただ、「さすがにそれはやめられない」ということも多いのです。 |
|
それならば、(回数や量を)減らせないか?を考えてみます。
「やめられないなら、減らせないかな?」です。
「一度に20キロの水を持ち上げていた(不安全)」→「10キロに減らして軽くする」
「ボルトが30センチもあって邪魔だ(不都合)」→「15センチに短くする」
「体重が増えて仕方ない(不健康)→「ゴハンの量を減らす」(これは冗談)
「やめられない」「へらせない」・・・となると、ここで登場するのが「カエル」です。
「カエル」には色んな「カエル」があるので、今度はみんなで、どんな「カエル」があるかを考えます。
ここでも旋削メンバーみんな、スラスラ書いていきます!
すげー!
|
|
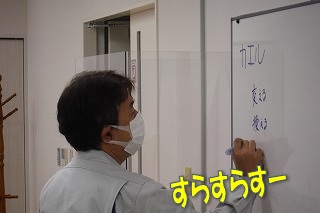
|
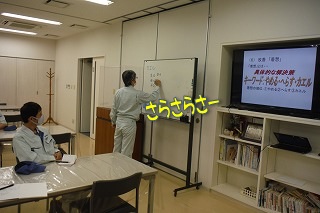
|
|
例えば、「返る」という言葉があります。
これは、「ひっくり返す」という改善を連想させてくれます。
実際の改善で、「使用済みの刃物をひっくり返して使ったら同じように使えた」というものもありました。
|
|

|
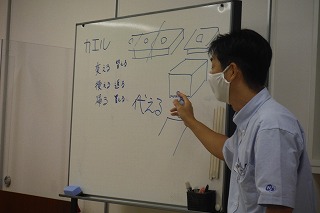
|
|
改善のステップ③は「着手」です。
ここのキーワードが「とりあえず」。
ここでは「とりあえず」な改善事例を紹介します。
例えば「番号付け」。
マンガの単行本を持っている人は多いと思いますが、本棚に並べる時に、
「5」「3」「2」「1」「4」
なんて並べ方をする人は、そうそういないと思います。
たいていは、
「1」「2」「3」「4」「5」
って並べますよね。
すると、「3」を取り出したら、たいていは「2」と「4」の間に戻すはずです。
そうなんです。多くの書類が入ったファイルに「1」「2」「3」と番号をつけることで、位置決めができるようになります。
これが「番号付け」です。
|
|

|
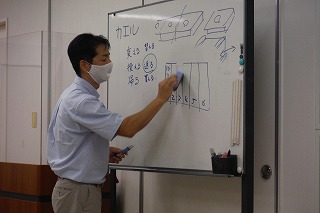
|
|
「線引き」も「とりあえず」改善のひとつ。
難しい位置合わせも、一本の線(基準線)を引くことで「線に合わせればいい」と、とたんに位置合わせがやり易くなります。
|
|

|
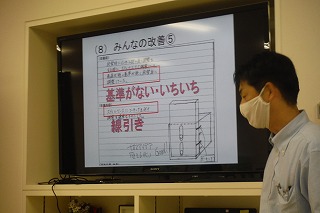
|
|
勉強会のラストは、いつものように理解度テスト!
勉強会の有効性を測定するのも目的のひとつですが、インプットしたことをアウトプットすることで、より記憶に刻み込むのも目的なのです!
ってことで、改善勉強会でしたー!
旋削メンバーのみなさん、お疲れさまでしたー!
|
|

|

|
W 
![]()